顎関節症になる原因
顎関節症は以下のような原因で発症することがわかっています。
1.歯の治療によって引き起こされるもの(医原性)
2.ストレスやそれに伴う癖や習慣によって引き起こされるもの(体の変化によるもの)
の2種類です。
今回は前者について解説します。
後者についてはこちら
医原性と言ってもは歯科医のミスという意味ではなく
、保険制度の仕組みや、料金とかけられる技術のバランス上の限界で生じるものや、日本の歯学教育の問題、審美や美容の要求に答えた結果生じてしまうものなど、多種多様の原因があります。
その原因となったものを理由も含めて解説します。
治療技術上の原因では以下の4つがほとんどを占めます。
①虫歯の詰め物が原因でなるもの
②根の治療、被せ物やブリッジの治療後になるもの
③入れ歯の治療や、入れ歯のメインテナンス不足で起きるもの
④歯列矯正の治療法が原因で起きたもの
①虫歯治療の詰め物が原因でなったもの
虫歯を治す際、奥歯の噛み合わせ面などの強い噛む力(咬合力)がかかる部分は金属材料を使用するのが基本です。
ここに審美材料のレジンや脆いセラミック、硬すぎるジルコニアを使うことで顎関節症の原因となることがあります。
レジンは柔らかく、咬合力ですり減り、セラミックは欠けたり、表面が砕けたりすることで、奥歯の噛み合わせが低くなり、顎の奥がズレます。
セラミックやジルコニアは表面はとても滑沢で、噛むと滑り易く、顎のズレが起こります。
このようなズレによって顎が身体と平衡が取れない位置になると顎関節症は発症します。
これは噛む機能のためではなく、審美や美容を目的で治療を受けたことで起きるのです。
②根の治療、被せ物やブリッジの治療後になるもの
一番奥歯の根の治療の時、歯が接触している咬頭部分を削ると、顎の奥の支えがなくなり、顎がズレてきます。根の治療とずれに関してはこちら
ズレたままで低い被せ物を入れてしまうと、治療前の位置とは違った顎の位置になってしまい、やがて顎関節症を発症してしまいます。
一番奥の歯を含むブリッジを作る際、正確ですり減らにくい材料を使った仮歯を入れて治療をすれば問題ありませんが、日本の標準的な仮歯の材料だと、完成したブリッジを入れるまでに仮歯がすり減り、顎がズレてきます。
ブリッジの調整に時間がかかることがあるのは、このような顎のズレが起きてしまったからで、技工士の製作物の出来が悪いからではないのです。
こうして起きた顎のズレは、身体との不均衡を参考させ顎関節症の原因になるのです。
③入れ歯の治療や、入れ歯のメインテナンス不足で起きるもの
入れ歯の人口歯は、通常硬質レジンというプラスチックでできており、などの原因が考えられます。
また入れ歯も金属の無い、目立たない入れ歯が流行っていますが、これも入れ歯のかみ合わせがどんどん沈み、かみ合わせを変化させてしまう危険な治療です。
つまり、日本では歯の治療そのものが顎関節症の原因となっている可能性は非常に高いのです。
残念ながら、現在の日本の保険制度では、顕微鏡を用いたり、かぶせものを外さないで根の治療を行うだけのコストと時間をかけられないのが現状です。
2番目の原因ですが、日本では今自由診療を積極的に取り入れるため、インビザラインやクリアライナーのようなきちんとしたかみ合わせを確立できるかいまひとつ確証のない治療が歯科医院で多く行われるようになりました。
患者さんも費用が安くて、お手軽に歯並びが治せる治療として、多く受け入れられましたが、実際はこの治療によって顎関節症になり、本格的な矯正をしなければリカバリーが不能になってしまう人も多くいらっしゃります。
また、抜歯をする矯正も、実は顎関節症の原因となったりします。これは抜歯によって口の中が狭くなり、それによって舌や顎の後ろの筋肉が緊張したり、顎の位置自体が後ろに行ってしまうことによって発症すると考えられます。
そしてもっとも重要なのものが3番目の習癖等が原因の顎関節症です。
これを解決することが最も難しい課題でした。
これは矯正で歯を動かしてゆく際、激しくかみしめたり、かみ合わせの位置をもとの位置にも戻そうとしたりするので、歯の動くスピードが遅くなったり、かみ合わせの後戻り、治療時のブラケットや材料が取れるなどの治療の障害と大きくかかわるために、非常に重大な問題です。
つまり、矯正治療を早く、しかも確実に、そして、顎関節症などを発症しないように行うためには、患者さん自身の生活習慣、生活環境そして精神面の安定がなければ難しいといえるのです。
すなわち、無理な生活習慣や、非常に悪い職場環境、極端に精神的に抑圧された幼少自体の経験(これは子供のころからあったとしても、長く大人になってまで刻みつづけられることがある)などの心に残った問題を本人が認識し、取り除かなければ、かみ合わせの治療をきちんと完成させることは難しいともいえるのです。
そのままの状態で行きますので、結局大人になっても奥に引いた噛み合わせになるのです。
ですから現代人は非常に顎関節症にかかる確率は高くなっているのです。
このことから、当医院では初診の方にシステムとして、健康管理をして頂くことを条件に入れております。なぜなら、健康管理をしていただかないと歯の治療が完結しないことに気付いたからです。
被せ物が原因で顎関節症に
このページは2022年11月14日に更新されました。
かぶせ物の治療で顎関節症(体調不良)になったのは以下の様な方々でした。
1、一番奥の歯を金属から白い詰め物に変えてから体調が悪くなった
一番奥の歯は、実は噛み合わせの高さを決めている、とても大切な歯です。
この歯を金属からレジン(樹脂)に変えてしまうと、噛みあわせが大幅に低くなってしまうこともあるのです。
噛みあわせが低くなってしまうと、顎が奥に入って嚙み締めがひどくなることがあります。嚙み締めがひどくなるとさらに奥歯が磨り減り、どんどん噛みあわせが低くなってしまう悪循環が起こります。
この悪循環が引き起こされると、顎関節症(体調不良)が発症して、不定愁訴を訴えるようになる方がいらっしゃいます。
2、奥歯のブリッジを入れてから、噛みあわせと体の調子が悪くなった
奥歯のブリッジは実は噛みあわせを作るのが非常に難しいのです。
ブリッジの型を正確に取った後、正確な噛みあわせの記録と、正確な高さの仮歯を入れる必要があります。
ブリッジの型を正確に取るにはシリコンという精度の高い材料で個人トレー(患者さんの歯列に合わせてオーダーメードで作った型を取るためのトレー)を使って型を取る必要があります。
またブリッジを作成する相手側の歯列も正確に型取りしなければなりません。ブリッジのような精密なかぶせ物を作る場合は個々の型の精度だけでなく、技工士さんの技術もとても大切な要素なのです。
ブリッジの型を取った後で正確な仮歯が入っていないとブリッジを入れるとき噛みあわせの調整(ブリッジの噛みあわせの面を削ること)が必要になることがあります。
大きく調整されたブリッジを入れた場合、噛みあわせに違和感が出たり、場合によっては顎関節症体調不良を含む)を起こすことがあります。
多くの先生も理解していないことが多いのですが、低い仮歯を入れられると、次のアポイントまでに患者さんの顎の位置はその低い高さに適応してしまい、たとえ正確な高さのブリッジを入れられていたとしても違和感を感じます。
違和感に対してブリッジを削って調整をしてしまうと、かみ合わせは完全に狂ってしまうのです。
3、出っ張っていた上の前歯をかぶせ物で治療をしてから噛みあわせと体の調子が悪くなった
上の前歯が出っ歯ているときはそれほど強く当たっていなかったのに、治療をした後で下の歯が強く当たるようになることがあります。
下の前歯が上の前歯に強く当たると、下顎全体を強く後ろに引いてしまうようになります。
顎を後ろに引くと、顎関節症(体調不良を含む)を発症する可能性が高くなります。
このようなかぶせ物や詰め物の治療で顎関節症から不定愁訴と呼ばれる症状を起こすことがあるのです。
歯列矯正で様々な不調が改善?
歯列矯正は体にとって「とても有用な治療」です。多くの人は歯並びが治る程度にしか考えていません。しかし、歯並びを治すことでお口の中を広げ、さらに噛み合わせが変わることで、様々な体の不調が取り除かれてゆきます。
実際に呼吸がしにくかったのが治ったり、疲れやすかった身体が疲れにくくなったりという効果がある治療なのです。
体も変えるロジカルな歯列矯正”で”不調まで治す”?はこちら
しかし、しかし、一方で「適切に行われない」と、「トラブルを生む治療」でもあるのです。
歯列矯正で噛み合せが良い方向に変化すると良いのですが、身体が敏感な方の場合、顎の位置が定まらず、矯正治療中に自分の顎の位置がずれてしまい、最終的に顎の位置がずれてしまう方も少なくありません。このようなトラブルは本人にしか分かりませんし、噛み合わせを理解して歯列矯正を行っている矯正医は実際はとても少ないのです。
特に最近ブームとなっている「ブラケットを使わない目立たない歯列矯正(マウスピース矯正)」はこのような微妙な噛み合わせの変化をコントロールできない治療法ですので、知慮を受ける前に十分な注意が必要です。
“歯科治療の基本”、”咬合学”を知らずして治療するべからず!はこちら
歯列矯正の反応は個人差が非常に大きく、身体のバランスが変わってしまうことも少なくありません。身体のバランスが変わることで噛み合わせの位置も変化してしまうことがあります。
敏感な患者さんの場合はこのようなバランスの変化に注意を払い、治療の初期には短期間で調整をする方が良いです。
また、下記のような治療を受けた人中には噛み合わせの問題が起きている人が多いので、注意が必要です。
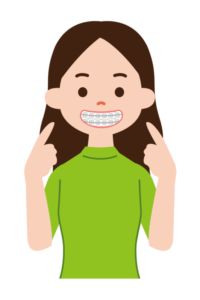
1、受け口の治療で発症
受け口(専門用語ではⅢ級)の治療を行われたる際、顎を後ろに下げる治療を行うことが多いのですが、比較的高い頻度で顎関節症(原因不明の体調不良)を発症することがあります。
受け口の治療では通常「顎を後ろに下げる」か、「下の奥歯を圧下(歯茎にめり込ませて沈めること)する治療」を行うので、噛み合わせが低くなり、呼吸路が狭くなって息苦しくなったり、後頭部、首などに凝りが出て、つらくなったりする症状が出ます。
歯列矯正トラブル例(受け口)はこちら
2、出っ歯を治すため歯を抜いた矯正治療。
出っ歯(専門用語でⅡ級)やガタガタな歯並び(専門用語で叢生)を矯正治療をする際、小臼歯を抜いて矯正治療を行うと、顎が下がったまま前に出なくなる噛み合わせになってしまう可能性が多く、口の中が狭くなって、舌を置いておく十分なスペースが無くなり、舌を後退位(喉の奥にしまった位置)に持ってゆく癖がついてしまい、呼吸路がふさがれる場合があります。ひどい場合は、「睡眠時無呼吸症候群」を発症したり、「呼吸がしずらい」、「鼻が詰まる」、「首、肩、背中が凝る」などの不調を訴える場合があります。
「出っ歯」の矯正トラブル例はこちら
3、子様の床矯正(取り外し可能な装置)による影響
ムーシールドや、トレーナー以外の床装置が矯正治療の初期治療でで有効なことは殆どないのが長年の臨床経験による考察の結論です。
上顎が狭いという理由で、急速拡大装置といった顎を横方向に急速に広げる装置を使った場合、歯の頭は移動しているように見えますが、根には無理な力がかかっており、CTスキャンで見ると根が上顎の骨の外に飛び出す場合があります。敏感な患者さんの場合、根が骨の外に飛び出した結果、神経が死んで、根の治療が必要になったりすることがあります。治療を受けるときは自分の体質等も含めて十分に検討する必要があります。
最新情報はこちら
番町D.C.の診療システムはこちら
ご通院前の注意事項はこちら
番町D.C.の料金システムはこちら
お問い合わせはこちら
歯列矯正が原因で顎関節症に
矯正治療を受けることで顎関節症(体調不良など)になる場合があります。矯正治療は審美的なことのみならず、噛み合わせなどの機能において人間の健康にかかわる非常に効果のある治療です。
しかしながら、噛み合わせを考慮しなければならないという非常に難しい治療技術でもあるのです。矯正治療の噛み合せについてはまだ十分な理論が完全には組みあがっていないのが現状でもあります。
矯正治療でトラブルが必ず起こるというわけではありませんが、敏感な人の場合慎重な治療を行なわないと、思わぬ症状に悩まされることがあります。また敏感な人でなくても矯正治療中に色々な症状が出ることがあります。ほとんどの場合は一過性のものでやがて改善しますが、中には本人にしか分からない問題が起こるケースも存在しています。
私の経験では、矯正治療で、体のパフォーマンスが変わることもあると思います。そのことを知ったり、経験したりしているのでアスリートが歯科矯正をしているのだと思います。
矯正治療で噛み合せを変化させられることで起こる変化は、あくまでも本人にしか分からないため、実はとても厄介で、歯科医がその状況を判断することはとても難しいのです。また噛み合せがずれていること自体が、矯正治療を受けようとする理由である場合は、噛み合せの理解が十分出来ている歯科医に矯正治療を行ってもらう必要が絶対にあるのです。
わたくしどもが診てきたケースで頻度の高いものから順に挙げますと以下のようになります。
1、受け口の治療を行うために、顎を後ろに下げる治療をうけたケース。
受け口(専門用語ではⅢ級)の治療を行われたる際、顎を後ろに下げる治療を行うことが多いのですが、比較的高い頻度で顎関節症(原因不明の体調不良)を発症することがあります。
受け口の治療では、顎を後ろに引くための治療や、奥歯を低くして、顎の位置を回転させる治療をすることが多く奥歯の高さが低くなりやすいです。その結果、呼吸路が狭くなったり、頚椎が緊張しやすくなったりして、顎関節症が発症するのではないかと私は考えています。
2、出っ歯を治すため歯を抜いて矯正治療をはじめるとともに体調が悪くなった。
出っ歯(専門用語でⅡ級)やガタガタな歯並び(専門用語で叢生)を矯正治療をする際、小臼歯を抜いて矯正治療を行うことが多いのですが、もちろんケースバイケースで抜歯が必要な場合もありますが、抜歯をして前歯を後ろに下げる際、奥歯も前に移動するため、噛み合せが低くなりやすいです。また、口元はすっきりするのですが、歯列のアーチが狭くなり口の中が狭くなり舌を置くスペースが狭くなり、呼吸路を圧迫しやすくなります。相対的に顎周囲の緊張が増す傾向となり、顎関節症症状が生じる場合があります。
3、前歯だけの矯正で出っ歯やスキッ歯を治してからに体調が悪くなった。
最近流行っているマウスピース矯正や部分矯正など、一部の歯だけを移動させて矯正する場合、前歯の当たりが急に変わり顎が前に出にくくなって後ろにに引かれてしまい他のケースと同じ様に顎周囲の緊張が強くなって、顎関節症の症状が出てしまうことがあります。
4、お子様の矯正で床矯正(入れ歯のように口に出し入れする装置)による影響
矯正を二段階で行う場合、顎を後ろに送るタイプの装置は上記のケースからもいえるように将来問題が出ることも少なくありません。床装置は有効な装置とそうでない装置との差があり、さまざまな装置を使ってきた経験で、ムーシールドなどの装置は非常に有効です。但し急速に拡大するタイプの装置は、敏感なお子さんの場合、問題を起こすことも少なくありません。近年のCT撮影では、急激で強い力を歯にかけることは必ずしも好ましくない作用が骨にあらわれることが分かってきました。
顎関節症の原因ってなんですか?
顎関節症は実はわかっているようで非常にわかりにくい病気なのです。
なぜなら顎関節症は顎の不具合から、全身にわたる不定愁訴まで、さまざまな症状があるため、すべてが噛みあわせだけに原因があるとは言い切れないからです。
1、噛みあわせが原因と考えられるもの。
a.歯の治療を受けてから顎の調子が悪くなったり不定愁訴の症状が出た場合。
矯正治療や虫歯治療、根の治療、ブリッジ、入れ歯などの噛みあわせを変えてしまうような治療を受けることで発症することがあります。実は治療によって噛み合わせが変わってしまったことは非常に多いのです。治療の際常に噛み合わせを変化させない配慮が必要ですが、日本で行なわれている一般的な歯科治療の場合、仮歯の精度や、根の治療のやり方、充填材料の選択が適切でないことが多く、治療をすればするほど噛み合せが変わってしまうケースが多いのです。
b.歯並びが深かったり、顎が左右どちらかに歪んでいたりしている人が、成長とともに顎の調子が悪くなってきたり、アレルギーや疲れやすいなどの症状が出た場合。
噛み合せが成長とともに悪化して、不定愁訴のような症状もだんだん悪化してきます。
これは体のバランスが徐々に崩れていったために、体の抵抗力や、恒常性を維持することが難しくなっておきてきたものです。
全身のバランスが崩れれば、一般的な人が何も感じないことやもの、食べ物などに対しても、強く反応したり
2、生まれつきのもの。
ほとんどの人があまり理解していないとおもいますが、顎のズレはすでに赤ちゃんから始まっていることがあります。お母さんのお腹の中でお母さんと一緒にさまざまなストレスを受けてるため、敏感なあかちゃんにはおなかの中ですでに顎が曲がり始めていることも・・。
赤ちゃんも大人と同じで体質も性格もまちまちです。また物理的なストレスだけでなく、お母さんが不安を感じていたり、周りの環境が良くないとそれだけでも筋肉や骨格に影響を与えてしまいます。
敏感な赤ちゃんは、お母さんが強いストレスを受けるとおなかの中で同じストレスを感じ、成長発育に問題が起こることがあり、生まれつき骨格がゆがんでいたり、体中の筋肉が固い傾向がある場合があります。
そのような赤ちゃんは生まれつき筋肉や靭帯、骨格に問題(奇形ではなく固まった状況なので緩めることで治ることも可能です)を持って生まれてきますから、さまざまな過敏症や、不具合を持っています。
先天的な疾患といわれるようなクローン病や、発達障害、自閉症などは、このような生まれつき筋肉や骨格が異常になっていることが実際は多いのです。(オステオパシーでクローン病が改善した例もあります。)
このような場合は、できるだけ早い時期に骨格のゆがみを治療すると、症状が軽くなったり場合によっては症状が消えることもあります。当医院では歯の治療と合わせてオステオパシー(アメリカの国家資格、日本では国家資格ではない)を紹介しています。
またこのような敏感な子は顎や歯に異常が起きる確率も高く、早い時期から噛みあわせの治療することも重要です。当院では、多動症や自閉症の症状が改善した例も少なくありません。
3、性格や後天的環境が原因である場合。
顎関節症の患者さんは非常に繊細な人が多いです。芸術家やクリエーターなど感性が高い人や緻密で繊細な仕事をする人は顎関節症になりやすいです。
また、敏感な人が医療やヒーリングなど、調子の悪い人を診なければならない職業や、SEなど細かい仕事でありながら過酷な労働を強いられる職種についている人も顎関節症を発症しやすくなります。
仕事による癖や、偏った筋肉の使い方によって長年の間に全身の筋肉にアンバランスが生じます。
これが顎にも影響を与え、位置が狂ったり、歯が移動したりすることで噛み合せが狂ってしまうことがあるのです。
このような場合、歯や噛みあわせ治療は重要ですが、体全体の調整も是非必要となります。
いずれにしても、顎の位置だけを治せばよいといった単純な治療ではないのが顎関節症なです。
